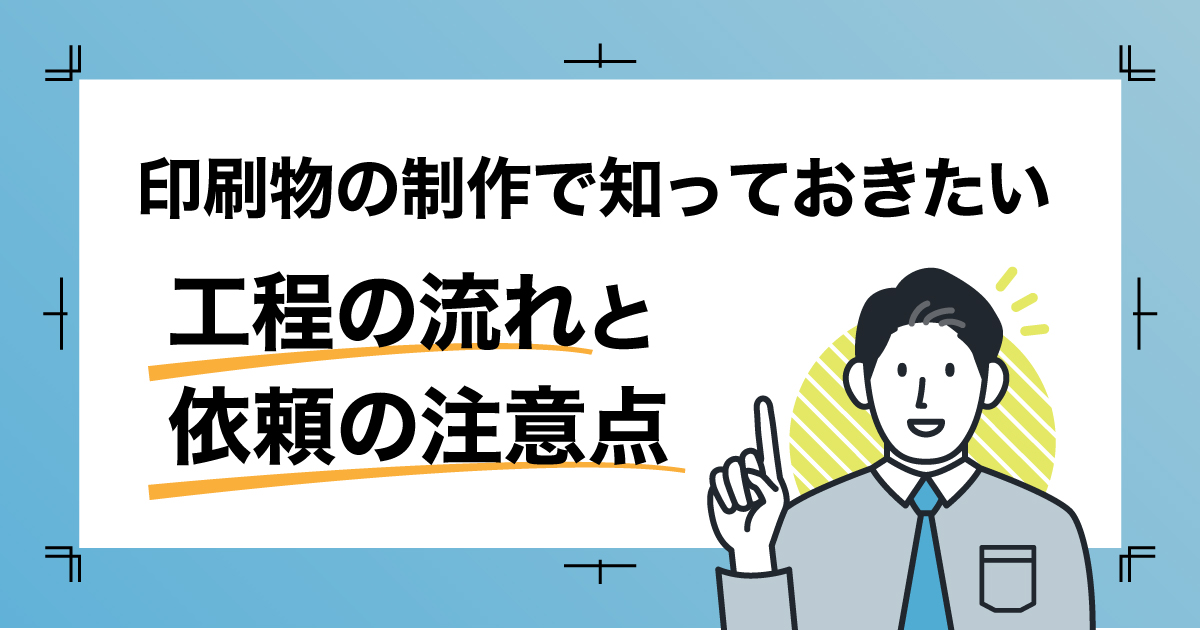初めて印刷物を制作する際に、納品までの流れや発注するときのポイントを把握しておきたい方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、発注された印刷物がお客様のもとへ届くまでの流れを3工程に分けて解説します。さらに、印刷会社へ発注する際のポイントも紹介しますので、制作を依頼する際の参考にしてください。
印刷物制作の流れは大きく分けて3工程

プリプレスは制作内容を決める工程で、企画やデザインの方向性を決めて印刷用の版を作成します。プレスは、作成された版を印刷機に取り付けて、印刷を始めます。ポストプレスは、最後の仕上げになる加工から納品までの作業です。
高品質な印刷物を制作するためには、どの工程も重要です。一つでも欠けてしまうと、イメージに沿ったものは出来上がりません。それぞれの工程でどのようなことを行うのか把握し、制作を進めましょう。
印刷物制作の流れ①プリプレス

印刷物制作の起点になる「プリプレス」は、主に以下の流れで進行します。
企画|制作の方向性を決める
印刷物の制作は「企画」から始まり、制作の目的やターゲット、デザインの仕様などを検討・決定します。企画段階で方向性を決めておかないと、想定した効果を発揮せず、失敗に終わる恐れがあります。
そのため、制作する際は時間をかけて競合調査や市場調査を行い、企画を立てなければなりません。企画で決める内容は、以下の通りです。
企画は社内会議で決める方法のほか、デザイン会社やデザイン部門を設けている専門の印刷会社を交えて行う場合があります。
専門知識を持っていない場合は、デザイン部門を設けている専門の印刷会社と協業するとよいでしょう。的確なアドバイスやサポートにより、企画から印刷・納品まで円滑に進みます。
デザイン制作|企画をカタチにする
企画で決まった方向性をデザインに起こしていきます。制作の流れは以下、表の通りです。
| 制作の流れ | 工程の内容 |
| 1.版下(はんした)の作成 | デザインを書き起こす |
| 2.校正 | レイアウトや文字に間違いがないかを確認する |
| 3.色校正 | 発色が正確か確認する |
版下の作成では、写真撮影やイラストの作成、テキストの作成、レイアウトの見本といった素材が必要です。これらの素材を使用して、思い描いた印刷物のイメージが書き起こされます。デザインが形になったら校正や色校正で、誤字脱字がないか、正しい色味で発色しているかを確認します。
どの工程も依頼者によるチェックは不可欠です。また、校正・色校正を確実に行うことで、「文字が違う」「色が違う」など印刷物の仕上がり後のミスを減らせます。
製版|印刷用の版を作る
プリプレスの最終工程になる製版では、印刷に必要な版を作成します。修正が行える最後の工程でもあるため、内容に間違いがないかを入念にチェックしましょう。
現在は、デジタル印刷などの登場により版を作る方法と版を作らない方法があり、印刷物の種類や部数により必要なコストは異なります。印刷会社と相談して、どの方法で進めるかを決めましょう。
また、版には多くの種類があります。チラシなどの印刷をする平版印刷では、A4用紙8枚程の大きなサイズを一度に刷るための版や、グラビヤ印刷のシリンダー状のものは大きな版を使用します。
また、小さなシールを印刷する場合は数センチ程度の小さな版を使用します。印刷方法や印刷機によって、版の大きさや材質はさまざまです。
印刷物制作の流れ②プレス

印刷前の準備|印刷機と版・紙のセット
安定した品質で印刷物を刷るために、印刷前の準備は欠かせない工程です。機械に版をセットし、インキが正しく発色しているかを確認します。また、印刷や色のズレをなくすための「刷り出し」と呼ばれる試し刷りでは、以下のような微調整が行われます。
印刷|印刷機で刷る
フルカラーでの印刷は、シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)、黒(K)の4色の版とインキを重ねて色を再現します。色を正確に出すため、以下のように色が濃いものから印刷するのが一般的ですが、印刷内容や印刷方式によっては順番を変えたりすることもあります。
また、インキの硬さや乾き具合は季節や気温、湿度によって変化するため、その日の条件に合わせた微調整が不可欠です。
さらに、印刷の途中で色味が変わってしまうケースもあります。そのため印刷途中も、色の確認を行い、不具合が発生した場合、機械を停止し、チェックと微調整を行います。
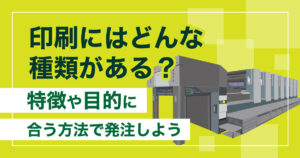
印刷物制作の流れ③ポストプレス

印刷物を目的の製品に仕上げ、お客様へ届ける工程を「ポストプレス」といいます。以下の流れでポストプレスは行われます。
加工|目的の印刷物に仕上げる
印刷終了後は企画で決定した目的や仕様に応じて、加工を施し製品化します。代表的な加工方法とその特徴は以下、表の通りです。作成する印刷物によって加工できる内容は様々です。仕上がりのイメージや使用する用途に応じて必要な加工を選択します。
| 加工の種類 | 特徴 |
| 抜き加工 | 印刷物を希望の形にくり抜く加工方法 丸やハート、雪の結晶など断裁加工ではできないカーブを用いた表現が可能 チラシや名刺、POPのほか、パッケージなどの別工程が必要な場合にも利用 レーザーカット・平盤打ち抜き・ブッシュ抜きなどの種類が豊富 |
| 断裁加工 | 指定のサイズで直線上にカットする加工方法 断裁機を活用して余白部分を切断 仕上がりは正方形または長方形 |
| 製本加工 | 本の状態に仕上げる加工方法 折り加工も製本加工の一つ 中綴じ・無線綴じ・アジロ綴じなど用途によって製本方法を選択可能 |
このほか、印刷物の表面に光沢感や凹凸を施す表面加工や、切れ目を入れるスリット加工、角だけ丸みを持たせる角R加工など、加工方法は豊富にあります。加工を施すことで印刷物の持つ可能性を引き出します。

納品|印刷物をお客様のもとへ
完成した印刷物をお客様のもとへお届けする流れは以下の通りです。
検品作業では、お客様の要望通りに仕上がっているか品質を厳しく確認します。検品では人の目で確認する「目視検品」と画像処理の機械を使用して行う「画像検品」などの種類があり、製品に求める品質に応じて検品方法を使い分ける場合があります。
品質に問題がなければ、次は梱包作業です。印刷物は少しの摩擦でインキが剥がれたり、色移りしてしまったりと繊細です。そのため、印刷会社または加工会社では、細心の注意を払って梱包作業に取り組みます。
梱包された完成品は、依頼元のニーズに合わせた方法で発送されます。印刷会社や加工会社の中にはアフターフォローを行っている会社があるため、アフターフォローがある場合は、どのような内容かを確認しておきましょう。
印刷工程の流れと発注のチェックリスト

最後に、印刷の流れに沿って確認しておきたいポイントを紹介します。デザイン会社や専門の印刷会社へ依頼するときだけでなく、自社で印刷物を制作する際にも活用できますので、ぜひお役立てください。
| 工程 | チェックポイント |
| 発注前・制作前 | コンセプトやターゲットを決める サイズ・部数などの仕様を決める 制作の目的や意図が伝わるよう書面やデータにまとめる 制作スケジュールを決める 見積書の内容を確かめる |
| 企画・デザイン制作 | コンセプトやターゲットに合わせた表現か 一目で伝えたい内容が伝わるか情報はすべて正しく入っているか |
| 印刷前 | 第三者を交えたダブルチェックはあるか 不適切な表現はないか 色味はイメージ通りか |
修正や刷り直しが発生してしまうと、予算以上のコストがかかってしまいます。このようなトラブルを避けるためにも、発注前や企画・デザイン制作の段階で、方向性を擦り合わせておくことが重要です。
まとめ

印刷の流れは主に3つの工程に分類できます。それぞれの工程を把握しておくことで、スムーズに制作を行えるでしょう。
制作する際は、流れを踏まえた計画と事前準備がコストダウンにつながります。また、デザイン部門を設けた専門の印刷会社に依頼すると、納品までの日数を短縮できる場合があります。目的に合わせて依頼先を決めるとよいでしょう。