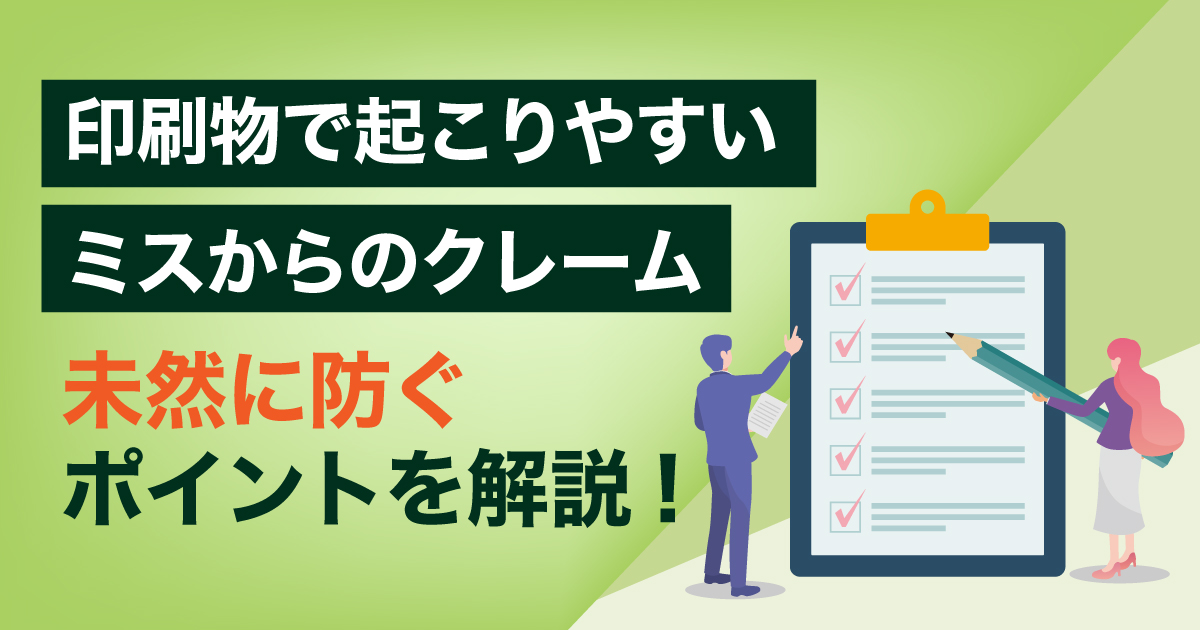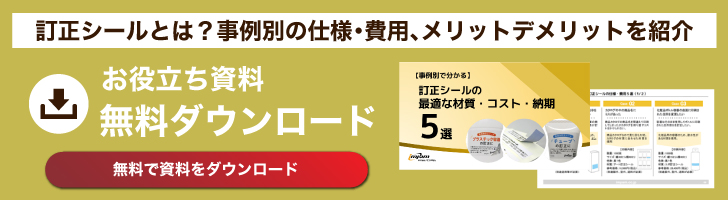作成したデータを入稿するだけで印刷できるサイトはたくさんありますが、内容に不備がある状態で入稿してしまうと、印刷完成後に内容の変更ができないため、クレームやトラブルに発展してしまう恐れがあります。
本記事では、納品後に印刷物のミスが発覚することでクライアントから受けるクレームを未然に防ぐためのポイントを解説します。
印刷後のクレームが発生するのは、基本的にクライアントが想定したものと完成した印刷物が違う場合です。ミスは誰にでも起こるものであり、避けられない場合もありますが、お互いの信頼関係のためにもミスを未然に防ぐ努力は必要不可欠です。初めて印刷データを入稿する方や、印刷物が問題なく完成するか不安な方も、事前に準備をしておくことでクレームやトラブルを防げます。印刷物を制作する際の参考にしてください。
※この記事での「クレーム」とは印刷のやり直しなどによって起こるお客様の不都合な事態の指摘を意味しています。
印刷ミスによるクライアントからのクレームは金銭的な損害が発生する場合もある

印刷物はWebサイトと異なり、誤植が発生しても修正は難しく、再印刷(刷り直し)が必要です。刷り直しは信頼を失うだけでなく、追加コストや納期遅延などのリスクがあります。刷り直しの主な原因に「誤字脱字など内容間違い」「印刷データの不備」が挙げられます。
誤字脱字など内容間違いの例は、以下の通りです。
- 価格表記の間違い
- 日時・曜日の間違い
- 電話番号の間違い
- 単純な文字の打ち間違い
- 漢字の変換間違い など
記載された内容に間違いがあると、会社とクライアントの間でトラブルが発生する可能性があります。このような印刷ミスが発生した場合、刷り直しが必要です。納品予定日に間に合わなかったり、納品後に発覚することで、損害賠償に発展するケースもあります。
印刷データ不備の例は、以下の通りです。
- テキストがアウトライン化されていない
- 塗り足し部分までデータが作成されていない
- リンク画像が添付されていない など
※アウトラインとは、印刷用データで文字をテキストデータからパスの図形データに変換しておく作業のことで、どのPCでデータを開いても文字の見た目が変わらなくなる処理です。
※塗り足しとは、用紙の端まで印刷がある場合、仕上げのラインより外にも数ミリ余分にデザインを入れておくことで、カットや抜きによる微妙なズレが生じた場合にも違和感なく仕上げられるようにするために付けるものです。
印刷データの不備が起きると、印刷データを再度作成し、印刷会社へ再入稿しなければなりません。印刷・納品ともに遅延する可能性があるでしょう。
このようなデータ作成上のミスは、ライターやデザイナーなど制作担当だけでは気づきにくいため、第三者によるデータチェックが必要です。クライアントが印刷内容をチェックする際には出力されたプリントアウトで行うことが多く、入稿時のデータが正しいかどうかはクライアントではチェックできません。これらも複数人でチェックを行うことで、ミスを防止できる確率が高くなります。
印刷工程で起こりやすいミスやトラブルから起こる6つのクレーム例
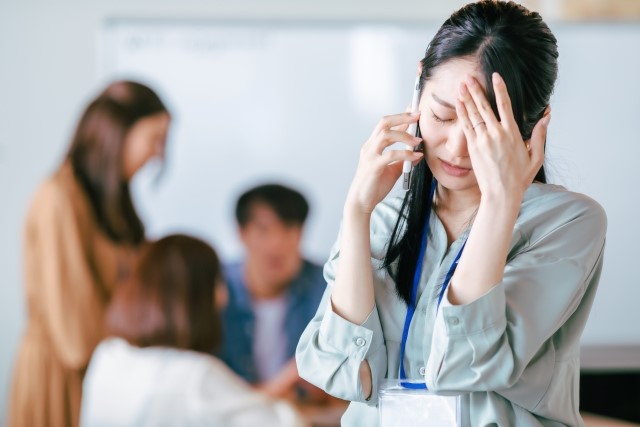
印刷工程におけるミスやトラブルから、クレームにつながる例を6つ紹介します。
- 注文データと入稿データのサイズが違う
- フォントや画像が予定と違うものに変換されてしまう
- 色が合わない
- 印刷物が汚れている
- 折り加工がズレている・折りジワがある
- 納品時にトラブルが起こる
クライアントからのクレームが発生する原因を理解して、不備がないように事前に確認しましょう。
注文データと入稿データのサイズが違う
印刷会社は、修正が不要な入稿データ(完全データ支給)で印刷を進めるのが一般的です。
データに不備が発見された場合、再入稿しなければなりません。その分、納期も遅れてしまうでしょう。またデータとして問題がなければ気づかず間違ったまま印刷まで進んでしまう場合もあります。
データ不備でよくある事例は、以下の通りです。
- 用紙のサイズが異なる
- 用紙のサイズが混在している
- 塗り足しが不足し、上下左右に余白が出てしまう
- 注文サイズと入稿サイズが間違っている
印刷会社が配布している入稿用のテンプレートがあればそれを使用したり、実際に出力してサイズを確認することで、このようなトラブルを回避できます。注文サイズと入稿サイズが間違っていた場合は、有料のデザイン修正サービスが利用できる場合もあります。
フォントや画像が変換されてしまう
入稿データのミスでフォントや画像が変換されてしまうことも、デザインと印刷物が違うことになってしまうためクライアントからのクレームに発展します。フォントや画像が変換されることがクレームにつながった事例は、以下の通りです。
- 画像の解像度不足により、印刷時の画像が粗い
- 入稿先にないフォントを使用したために、別のフォントに置き換わる
- 画像の埋め込みや添付を忘れ、画像が表示されない
印刷物に使用する画像の解像度は、300〜350dpiが適切です。印刷に耐えうる解像度であるか事前に確認しましょう。また、テキストはアウトライン化することで、フォントが置き換わるのを防げます。
入稿データを作成する前には、必ず画像が添付または埋め込みされているかを確認しましょう。
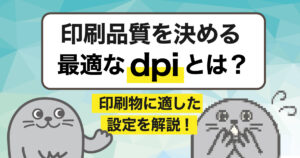
色が合わない
印刷は4原色(CMYK)で色を表現するため、モニターに表示される色(RGB)とは異なります。また、印刷会社にある専用の印刷機と社内のプリンターでも印刷方法やインキは違います。社内のプリンターでは色の確認は難しいため、文字やレイアウトの確認を行う程度に留めましょう。
印刷物の発色は、本番の印刷前に「色校正」という工程を行うことで確認できます。また、色見本や色チップを添付して入稿すれば、表現したい色を伝えることも可能です。増刷時には、前回の印刷物を見本として添付するとスムーズです。

印刷物が汚れている
印刷物の汚れは、インキの付着や印刷物を積み上げた際の擦れが原因で発生します。汚れの種類と特徴は、以下の通りです。
| 名称 | 特徴 |
| 裏移り | 刷り上がった印刷物の上に積み重なるためにインキが裏面に移ること |
| ブロッキング | 裏移りした印刷物が接着すること インキの濃度が濃い、量が多い場合に起こりやすい |
| 裏抜け | 印刷内容が裏面に、にじみ出て透けて見えること 上質紙など浸透しやすい用紙や厚さが薄い用紙で起こりやすい |
| ピンホール | デザイン面に小さな白い点や丸のようなものが付着している |
汚れやすい用紙や濃度のある色を広範囲に使用したデザインの場合は、ニス引きや印刷方式をUV印刷に変えて汚れを防止できます。
折り加工がズレている・折りジワがある
折り加工がある印刷物を作成するときは、調整が必要です。用紙が厚いと、複雑な折り加工の際にシワや折り目が割れる場合があります。3つ折りやDM折りなど複雑な折り加工では、見栄えが悪くなる可能性があるでしょう。
また、パンフレットで見開きの文字や写真がズレてしまうと見栄えが劣ってしまいます。特に中央に掲載される写真は注意が必要です。
背割れを完全に防ぐのは難しいため、複雑な加工をする際は用紙の厚さを薄くしたり、背割れ防止の加工を施したりしてください。また、折りや綴じ加工部分に文字や写真、絵柄の掲載は避けた方がよいでしょう。
納品時にトラブルが起こる
無事に印刷できたとしても納品時にトラブルが発生してしまい、クライアントからのクレームにつながる場合もあります。
イベントで使用する印刷物などは、時間指定で納品を希望するケースがあります。間に合うように宅急便を手配していても、渋滞や集配の影響で納品が遅れてしまうといったトラブルが発生するかもしれません。このような場合は、指定された時間に納品できるよう、クライアントとの打合せでチャーター便や分納を検討してもらう必要があります。
また、複数の納品先があり、内訳枚数が間違っている場合もトラブルになります。伝え漏れが原因で起こりやすいため、クライアントと交わした数量や納品場所の変更はメールなど記録に残すようにしましょう。
クライアントからの印刷クレームを防ぐ4つのポイント

クライアントからの印刷のクレームを防ぐためのポイントを4つ紹介します。
- 入稿前に印刷データを再確認する
- 入稿時に色見本や加工見本を送る
- 色校正を行なう
- 特色印刷はカラーチップを使う
印刷の基本を把握して、スムーズな印刷の進行を心掛けましょう。
入稿前に印刷データを再確認する
入稿前にチェックリストを用意して、確認するとデータの不備を防げます。
一般的なチェックリストは、以下の通りです。
| チェックリスト | ✓ | |
| 1 | 仕上がりサイズでデータを作成しているか | |
| 2 | 上下左右3mm以上の塗り足しでデータを作成しているか | |
| 3 | テキストデータはすべてアウトライン化しているか | |
| 4 | CMYKで作成しているか | |
| 5 | 不要なレイヤーやオブジェクトは削除したか | |
| 6 | 画像は埋め込み形式または添付しているか | |
| 7 | オーバープリントの設定は適切か | |
| 8 | ファイル名は文字化けしない文字を使用しているか | |
| 9 | 出力見本を用意しているか |
ただし、チェックするポイントは印刷物によって変わるため、入稿予定の印刷会社に確認が必要です。
入稿時に色見本や加工見本を送る
刷り色の発色が不安な場合は、色見本も送りましょう。印刷現場では、色見本をもとに経験豊富な印刷オペレーターが色味を調節します。料理や貴金属など適切な色の表現が不可欠な印刷物は、印刷現場に立会い、刷り色をチェックしながら進める方法もあるため印刷会社に相談してみましょう。
パンフレットやカタログは折り位置や表紙ページを指示するため、加工見本を添付します。校正用PDFやJPG画像を送ると、印刷会社で内容を確認できます。
色校正を行なう
色校正とは、印刷物の刷り色を確認する試し刷りの作業です。色校正は3種類あり、色の再現度やコストはそれぞれ異なります。
色校正の種類や特徴、再現度は以下の通りです。
| 色校正の種類 | 特徴 | 再現度 | コスト |
| 簡易校正 | インクジェット印刷機で印刷を行う本番と近い色に調整したインキを使う | △ | ◎ |
| 本紙校正 | 本番と同じ用紙で印刷を行う印刷機とインキは本番とは異なる | 〇 | 〇 |
| 本機校正 | 本番で使用する印刷機で行う本番と同じ用紙やインキを使用する | ◎ | △ |
色校正を行えば、印刷物の品質は向上します。しかし、時間とコストもかかるため、どの程度の確認が必要かを検討して行いましょう。

特色印刷はカラーチップを使う
特色印刷は通常のプロセスカラ―では表現できない色や、金・銀・パールなどのメタリック色や蛍光色も利用できます。特色を選ぶ際は、モニターと色見本では発色が異なるため、必ずメーカーのカラーチップから選びましょう。
代表的なカラーチップは、日本の印刷会社で多く利用されているDICと、グローバルスタンダードとして利用されているPANTONEがあります。印刷会社によって、カラーチップの採用は異なるため、対応しているカラーチップに合わせてください。
また、同じ色番号でも、カラーチップの発行時期によって色が微妙に異なる場合もあります。色に厳しい場合は、印刷前に最新の色見本帳で印刷会社と確認しましょう。
印刷のクレームが不安な場合は印刷会社に相談しよう

印刷に適したデータの作成は注意すべきことが複数あります。少しでも不安がある方は印刷会社に相談をしましょう。印刷会社に相談するメリットは、以下の4つです。
- 印刷物の悩みを相談できる
- 特殊な印刷・加工ができる
- 印刷前に入稿データを確認してもらえる
- 刷り色の要望も詳細に伝えられる
専門知識がなくても、印刷会社に相談・依頼をすることで、高品質の印刷物を制作できます。特に企画やデザインから印刷物を制作したい場合は、デザイン部門のある印刷会社を選ぶと一貫して制作を行えます。
まとめ

印刷のクレームは、納期遅延や追加コストの発生だけでなく、クライアントからの信頼を失うリスクがあります。しかし、事前に準備を行えば、トラブルは未然に防げます。
クレームを防ぐポイントは、以下の4つです。
- 入稿前に印刷データを再確認する
- 入稿時に色見本や加工見本を送る
- 色校正を行なう
- 特色印刷はカラーチップを使う
これらのポイントを把握して、スムーズな制作を行いましょう。
事前に気をつけるべきことを知り、スムーズな取引を行うことでクライアントとの信頼関係をより高めることができます。
また、ミスや勘違い、計画が予定通りに進まないなどはどれだけ予防しても起こることがあります。そういった場合の対処法を事前に考えておくことでトラブルにも迅速に対応できる場合があります。